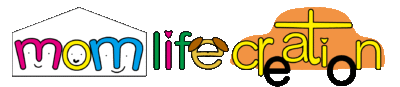言葉が遅いのは大丈夫?と気になったら 知っておきたい発達の知識

子どもが日々成長する姿を感じられるのはうれしいものです。
しかし「他の子よりも言葉が出るのが遅いかも」と不安を感じているママやパパもいるかもしれません。
この記事では、言葉の遅れとはどのようなものか、言葉の遅れと発達障害に関連があるのかなどについて解説します。
「言葉の遅れ」とはどのような特徴がある?
言葉の遅れとは、どのような状態を指すものでしょうか。子どもの年齢に応じた言葉の発達段階を参考にし、言葉の遅れの具体的な特徴を見ていきましょう。
言葉の発達の標準的な流れ
言葉の発達には大きく分けて「言葉を理解する力」と「言葉を表出する力」があります。
年齢とそれぞれの発達の目安について下表で説明します。
◆言葉の理解
| 年齢 | 言葉の発達内容 |
| 生後3~4か月 | 音が出る方向を向く |
| 生後9~11か月 | 「ダメ」がわかる |
| 1歳~1歳6か月 | 簡単な指示がわかる |
| 2歳~2歳5か月 | 体の部位、大きい・小さいがわかる |
| 2歳6か月~3歳 | 長い・短い、色の名前がわかる |
| 3歳~3歳6か月 | 高い・低い、数の概念(3まで)がわかる |
| 4歳~4歳7か月 | 右・左、数の概念(5まで)がわかる |
◆言葉の表出
| 年齢 | 言葉の発達内容 |
|---|---|
| 生後3~4か月 | 人の顔を見てほほ笑む |
| 生後7か月 | 喃語(バババ、マママなど)が出現する |
| 1歳~1歳6か月 | 初語が出る |
| 1歳6か月~1歳10か月 | 単語と指さし、単語と身振りを合わせた表現が見られる |
| 2歳~2歳6か月 | 2語文(マンマ食べる)、3語文(絵本もっと読む)が言える |
| 3歳 | 自分の名前が言える |
| 4歳 | 一つの話題を維持できる |
| 6歳 | 内容を整理しまとめて説明できる |
このような発達段階はあくまで「目安」であり、必ずしも全員が同じペースで進むわけではありません。
言葉が遅れている子どもの特徴と判断の難しさ
2歳までに「マンマ」「ブーブー」といった意味のある言葉が出ない、または3歳までに「ワンワン きた」といった2語文が話せない場合は言葉が遅れている可能性があります。
しかし、言葉の遅れが個人差の範囲内なのか、発達に何らかの問題があるのかの判断は難しいものです。言葉の発達は子どもによって個人差が大きくあり、話し始めが早い子や3歳になってから言葉数が急に増える子などさまざまです。
例えば、1歳6か月健診において、5語以上の意味のある言葉を話せる子どもは男の子で80%、女の子で93%いるとされています。
しかし、言える言葉が1~4語であった子どものうち、70~80%が、その後の3歳児健診時では言葉の遅れを取り戻せるといった報告もあります。
早い段階で言葉の遅れを指摘されてしまうと、焦りや不安を感じてしまうもの。
けれども、大切なのは子どもの成長のペースを見守ることです。
言葉の遅れは発達障害によるもの?

子どもの言葉の遅れについて「発達障害が原因?」と不安に感じるママ・パパもいるかもしれません。
しかし、言葉の遅れ=発達障害とは断定できません。その理由を見てみましょう。
発達障害の特徴
発達障害とは、生まれ持って脳の仕組みに違いがあることで生活に支障が出てくる脳機能の障害です。
発達障害のひとつに、自閉スペクトラム症(ASD)があり、言葉の遅れと関連があるケースもあります。しかし、言葉の遅れだけで診断がつくものではありません。
自閉スペクトラム症の特徴としては以下のようなものがあります。
・相手の気持ちを考えない行動をする
・人見知りが強すぎる
・興味や関心の対象が偏っている
・特定の行動を繰り返す(同じ遊びばかり、順番への強いこだわりなど)
・おうむ返しや独自の単語を使う
言葉の遅れ=発達障害ではない
一口に言葉の遅れと言っても、必ずしも発達障害が原因とは言えません。
発達障害の他にも、耳の聞こえの問題や純粋に言語発達のみ遅れている場合、極端な恥ずかしがり屋の性格による場合などがあります。
言葉の遅れの原因は、聴力検査や発達検査(または知能検査)、子どもの行動特徴を観察することで原因を調べることができます。
言葉の遅れに対する支援はある?

言葉の遅れに対して、生活のなかで親ができる関わり方や自治体、療育機関ではどのような支援が受けられるか見てみましょう。
今からできる関わり方の工夫
言葉の遅れが見られる子どもに対して、普段の会話でできる働きかけを紹介します。
大人から言葉をかけることで、子どもが「人とコミュニケーションをする意欲」や「わかる言葉」が増し「言える言葉」が増えることが期待できます。
| 接し方 | 具体例 |
| 動きをまねてみる | トントンと積み木を叩いていたら、同じようにまねる。 |
| 出す音や声をまねてみる | 「マンマンマン」などと喃語が出ていたら、同じように声を出す。 |
| 気持ちを言葉で表す | おいしそうにご飯を食べていたら「おいしいね」と言葉にする。 |
| 間違えた言葉をさりげなく直す | 子どもが人参を「にんにん」と言ったら「にんじんだね」と正しい言葉で直す。 |
| 子どもの言葉を広げて返す | 子どもが走っている車を見て「ブーブー」と言ったら「赤いブーブーだね」「ブーブー速いね」などと言葉を広げる。 |
日々の遊びや会話のなかで、できるところから取り入れてみましょう。
自治体や医療機関での支援
現在、自治体によっては言葉の専門家である言語聴覚士が健診に同席し、お子さんの様子を観察して、接し方や遊び方のアドバイスが得られるケースがあります。
また、健診以外でも発達に関する相談窓口が設置されている自治体もあります。自治体の子育て相談窓口や保健センターに相談してみましょう。
パパやママだけで悩むのではなく、周囲の力を借りることが大切です。
周囲の支援が子どもの発達を促すきっかけに

子どもの発達についての不安はつきもの。特に言葉は毎日のコミュニケーションにおいて重要な役割を持っているため、周囲より遅いことが心配になってしまいますよね。
ただ、心配は自身や家族だけで抱えるのではなく、地域の専門家からのアドバイスで解決の糸口が見つかるかもしれません。子どもの成長のペースは1人ずつ異なります。周囲の支援を借りながら、子どもの成長を見守っていけるといいですね。
著者:渡邊かこ
言語聴覚士
大学病院や一般病院にて急性期・回復期・生活期に従事。趣味は旅行、写真、山歩き。一児の母。
参考:
・乳幼児期のコミュニケーションの発達─ 会話における「明確化要求」を中心に ─
・神戸大学 大学院医学研究部・医学部 こどもの言葉と発達の見方・促し方
・千葉県千葉リハビリテーションセンター 言語発達が遅い子ども
・日本言語聴覚士協会 言語聴覚士のための乳幼児健診入門ガイド
・日本小児神経学会 Q72:言うことは理解できるのですが単語が数語しか出ないのは病気でしょうか?
・熊本市こども発達支援センター お子さんの発達に心配のある保護者の方ヘ
まだデータがありません。