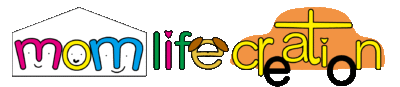妊娠高血圧症候群で入院になったら?期間や赤ちゃんへの影響を解説

「臨月になって、急に妊娠高血圧症候群と診断されたけれど、赤ちゃんへの影響は大丈夫?」「いつまで入院するの?」
初めての妊娠で突然の入院を告げられると、不安を感じる方は少なくありません。妊娠高血圧症候群は、母体と胎児の両方に影響を及ぼす可能性がある病気です。しかし、医療機関で適切に管理すれば安全に出産できる確率が高まります。
この記事では、妊娠高血圧症候群のリスクや入院中の検査について解説します。
妊娠高血圧症候群は母子ともに影響が心配される病気
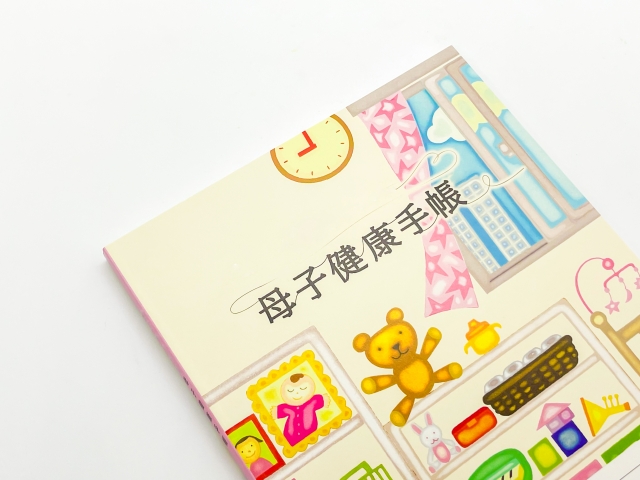
妊娠高血圧症候群とはどのような病気か、詳しくみてみましょう。
症状はないのに静かに進行する
妊娠高血圧症候群とは、妊娠中に血圧が高くなる病気です。具体的には、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上である場合に診断されます。妊娠高血圧症候群は、進行しても自覚症状がほとんどありません。そのため、妊婦健診時の血圧測定や尿検査で早期に発見することが大切です。
発症する原因は明らかになっていませんが、妊娠初期にうまく胎盤を形成できないことが関係しているのではないかと考えられています。
妊娠高血圧症候群は、妊婦さんの10~20人に1人の割合で発症し、決して珍しい病気ではありません。
しかし、母子ともにさまざまな合併症を発症するリスクが高く、医療機関での慎重な管理が必要な病気でもあります。
妊娠高血圧症候群には4種類ある
妊娠高血圧症候群は、発症の時期や症状によって4つに分類されます。
妊娠高血圧症
妊娠20週以降に初めて高血圧を発症して出産後12週までに軽快し、最後まで高血圧以外の大きな異常を示さない型を指します。
妊娠高血圧腎症
妊娠高血圧腎症は、妊娠20週以降に初めて高血圧が現れ、タンパク尿がみられる場合に診断されます。また、タンパク尿がなくても次のような症状があるとこの型に当てはまります。
・肝臓や腎臓の動きが悪くなる
・血液が固まる働きに異常がみられる
・脳に関する症状がある(脳卒中やけいれんなど)
・胎児の成長がゆっくりで、発育が心配される
高血圧とタンパク尿は、多くの場合、出産後12週までに軽快します。
加重型妊娠高血圧腎症
妊娠前あるいは妊娠20週未満から高血圧のある方が、妊娠20週以降に妊娠高血圧腎症の症状を発症した場合に診断されます。
また、妊娠前から腎臓の病気によるタンパク尿があり、妊娠20週以降に高血圧となった場合も含まれます。
高血圧合併妊娠
妊娠前または妊娠20週未満から高血圧があるものの、高血圧以外の大きな異常を伴わない型を指します。
なお、妊娠34週未満の発症を早発型、34週以降の発症を遅発型と呼び、早発型の方が、重症化しやすいとされています。
母子の命に関わる妊娠高血圧症候群の合併症
妊娠高血圧症候群が重症化すると、母体・胎児ともにさまざまな合併症を引き起こすリスクが高まります。それぞれの合併症について詳しくみていきましょう。
けいれんが頻発する「子癇(しかん)」
子癇は妊娠20週以降に初めて起こるけいれん発作で、てんかんや脳出血など他に原因がない場合を指します。子癇の前兆として、次のような症状がみられることがあります。
・頭痛
・見え方の異常(まぶしい感じがする、目がチカチカする)
・胃痛
子癇が起こると意識を失ったり全身がけいれんしたりすることがあり、母子の命に関わる状態になります。状態によっては、すぐに出産する必要があり、その日のうちに帝王切開になることもあります。
突然胎盤がはがれる「常位胎盤早期剥離(じょういたいばんそうきはくり)」
常位胎盤早期剥離とは、正常な位置に付いている胎盤が、妊娠中や出産の途中で子宮の壁からはがれてしまう状態を指します。主に、次のような症状がみられます。
・性器からの出血
・お腹の張り
・強い下腹部痛
常位胎盤早期剥離が起こると、母体が大量に出血したり、胎児に十分な酸素が届かなくなったりする危険があります。妊娠中に発症した場合は、胎児の命を守るために帝王切開が行われます。
また出産の途中で発症した場合は、胎児をできるだけ早く取り出すために、「吸引分娩」や「鉗子(かんし)分娩」などの方法で出産を進める場合も。
吸引分娩では胎児の頭にやわらかいカップのような器具を使い、鉗子分娩では胎児の頭を挟める専用の器具(鉗子)を使って、陣痛のタイミングに合わせて胎児を引っ張ります。
肝機能障害や血小板減少を伴うHELLP症候群(ヘルプ症候群)
HELLP症候群は、妊娠後期から出産後にかけて発症しやすい合併症です。
赤血球が壊れる、肝機の動きが悪くなる、血が止まりにくくなるなど、身体にさまざまな変化が現れます。これらの英語の頭文字をとって「HELLP症候群」と呼ばれています。HELLP症候群は、診断が遅れると多くの臓器に悪影響がおよび、命に関わることもある病気です。
主な症状には、次のようなものがあります。
・突然の腹痛
・吐き気
・嘔吐
この病気は、出産によって症状が良くなるため、母体や胎児の健康状態や妊娠週数などをみながら、最適な出産方法や時期が選ばれます。
妊娠高血圧症候群が赤ちゃんに与える可能性のある影響

妊娠高血圧症候群による赤ちゃんへの影響についてみていきましょう。
胎児発育不全
胎児発育不全とは、胎児が子宮内で十分に成長できない状態のことです。
平均と比べて発育が遅く、推定体重が軽い場合に診断されます。妊娠高血圧症候群により胎盤の血流が悪くなると、胎児に酸素や栄養が十分に届かず、胎児発育不全を引き起こすことがあります。
胎児発育不全に対する明確な治療法はありません。安静に過ごすことが基本で、胎児の状態によっては早めに出産が必要になる場合もあります。
胎児機能不全
胎児機能不全とは、胎児の元気がない、または元気がなくなるおそれがある状態のことをいいます。
妊娠中や出産時の検査(主に超音波検査や胎児の心拍をチェックするモニター)で、胎児の様子に異常がみつかると、このように診断されます。
妊娠高血圧症候群によって、胎盤からの酸素供給が不十分になることが原因の一つです。
胎児死亡
母体側・胎児側のさまざまな合併症が原因となり、お腹のなかで胎児が亡くなってしまうこともあります。
入院期間は血圧が落ち着くまで
一般的に、出産後に血圧が安定するまで入院する必要があります。
なぜなら、妊娠高血圧症候群によってさまざまな合併症のリスクが高まるからです。
医療スタッフが迅速に対応できる環境で適切な管理を受ければ、安全に出産できる可能性が高まります。
母子の健康状態を詳しく観察するための検査は以下のとおりです。
・胎児心拍のモニタリング(お腹の上に機械を当てて、胎児の元気さを確認する)
・エコー検査(胎児の成長の状態をみる)
・血圧測定
・血液検査
・尿検査
これらの検査で病状の進行や変化を早期に把握でき、適切に処置できるのです。
入院期間が長期化すると、費用面の不安を感じる方もいるかもしれません。
そのような場合は、病院の医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。
医療費の助成制度や民間保険の利用方法など、個別の状況に合わせた支援策を案内してもらえます。
入院はママと赤ちゃんを守るための時間
妊娠高血圧症候群は、ママと赤ちゃんの両方に影響を及ぼす可能性があるため、早期発見と適切な治療を受けることが重要です。
入院となった場合は、医療スタッフが24時間体制で母子の状態を見守り、治療方法や出産のタイミングを慎重に判断します。
長期入院になることもありますが、それは「ママと赤ちゃんを守るための大切な時間」です。
焦らず、自分と赤ちゃんの健康を第一に考え、医療チームとともに乗り越えていきましょう。
著者:山田ちふみ
看護師 保健師
国立大学の医学部看護学科を卒業後、総合病院やデイサービスにて看護師として勤務。現場での実務経験を活かし、現在は医療系のWebライターとして活動中。
参考:
・公益社団法人日本産科婦人科学会 産婦人科診療ガイドライン 産科編2023
・和歌山県立医科大学 産婦人科学教室 胎児発育不全(FGR)とは
まだデータがありません。